量子力学は、観測された結果の分布を正確に予測できる理論であり、長年にわたって数多くの実験的検証にも耐えてきた。前回見たように、その枠組みは観測の限界に根ざして構成されている。
にもかかわらず、量子力学が「不思議な理論」とされるのは、観測の前に何が起きていたのか、あるいは観測によって何が変わるのか、といった問いに対して、理論の中に明確な答えが含まれていないからだ。
観測前の状態を直接確かめる手段がない以上、そのあり方についてはさまざまな見解が成り立ちうる。そのような問いに応える形で提案されてきた多様な立場を、一般に「量子力学の解釈」と呼ぶ。
コペンハーゲン解釈──確かめられないことは考えない
この問いに対して最も大きな影響力をもってきた立場が、いわゆるコペンハーゲン解釈である。立場と言っても一枚岩ではなく、明確に定義された理論があるわけでもないが、以下のような基本姿勢を共有している。
- 観測されない量は物理的に意味を持たない。
- 波動関数は確率を計算するための道具であって、実在するものではない。
- 現実とは観測によって得られた情報である。
この構えをとれば、「観測の前にどうなっていたか」という問いそのものが、物理学的には意味をもたないことになる。理論は確率的に結果を予測するための枠組みであり、それ以上のことを語る必要はないという立場だ。
この考え方は「わからないことには手を出さない」という意味で、ある種の誠実さを持っているとも言える。だが一方で、「観測されたときに状態が確定する」と説明されることで、あたかも観測が現実をつくっているかのように読めてしまうこともある。
実際、入門書などでは「観測の瞬間に現実が決まる」といった説明がなされることもあり、それが量子力学の「不思議さ」を印象づけている。これは誤解というよりも、理論の枠組みがそう読める構造を持ってしまっていることの副作用だろう。
コペンハーゲン解釈の本質は、観測前の状態を知る手段がない以上、それについての問いは理論の外にあるという点にある。つまり、「確かめようのないことは考えない」。解釈というより、むしろ解釈を拒否する立場だとも言える。
多世界解釈──結果は分岐してすべて起きている
観測によって状態が「決まる」という考え方に疑問を抱く人たちは、もっと別の見方を取ろうとした。その中で有力なのが、多世界解釈(エヴェレット解釈)である。
この立場では、波動関数は常にユニタリに発展し続けており、途中で突然変化するようなことは起きない。観測の瞬間に何かが決まるわけではなく、観測とはただ世界が分岐する出来事にすぎないとされる。
たとえば、ある測定で「上」と「下」の2つの可能性があるとき、観測の結果として「上の世界」と「下の世界」が両方とも存在することになる。私たちはそのうちのどちらかの世界に属することになるが、他方の世界も消えずに残っている。
この解釈は、波動関数の重ね合わせをそのまま認め、矛盾なく扱おうとするものだ。理論に新たな要素を付け加えることなく、すべてを数式の中で完結させるという意味では、最も単純で力強い見方でもある。
ただし、「無数の世界が同時に存在している」という前提を受け入れる心理的なハードルは高い。なぜ自分がこの世界にいるのか、他の世界は何なのか、といった問いが新たに生まれることにもなる。
ボーム力学──粒子は常にどこかにある
もうひとつの大きな流れとして、ボーム力学(パイロット波理論)がある。これは量子力学を再構成し、粒子には常に位置があると仮定することで、状態の「飛び出し」や「突然の決定」を避けようとする。
この理論では、波動関数は存在し続けているが、それは粒子の運動をガイドする役割を果たす。粒子の位置は最初から決まっており、波動関数とともに進化していく。測定によって状態が決まるのではなく、測定はただ既にあった位置を明らかにするだけだ。
その代わり、波動関数は非局所的に粒子に影響を与える必要がある。つまり、遠く離れた場所の情報が瞬時に影響を及ぼす。この非局所性を認めることで、量子力学の実験結果を再現できるようになっている。
現代の量子力学と比べると発展の幅は限られているが、「粒子は常にどこかにある」と信じたい立場からは根強い支持を受けている。
その他の立場とその意味
ここで紹介した三つの立場以外にも、量子力学の解釈をめぐる試みは多様に存在する。観測結果を「主観的な知識の更新」とみなすQBism、観測の事実が「誰にとってのものか」に依存するとする相対論的量子力学(Relational Quantum Mechanics)、波動関数の自発的崩壊を導入するGRW理論などがある。
それぞれの立場には、それを支持する哲学的動機や理論的工夫がある。だが共通するのは、「量子力学は確かに成功しているが、それだけでは語りきれない部分がある」という問題意識だ。
観測前の状態に関して、量子力学は答えを持たない。持たないことを良しとする立場もあれば、何らかの形で補うべきだとする立場もある。どちらが正しいかは、まだわからない。
少なくとも現時点では、解釈をめぐる議論は、理論の外側にある哲学的選択肢としての側面を強く持っている。ただし、これは単なる哲学では終わらないかもしれない。将来の理論や実験が、どこかの解釈を支持するかもしれないし、全く新しい見方を導くかもしれない。

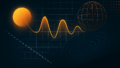
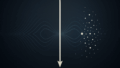
コメント